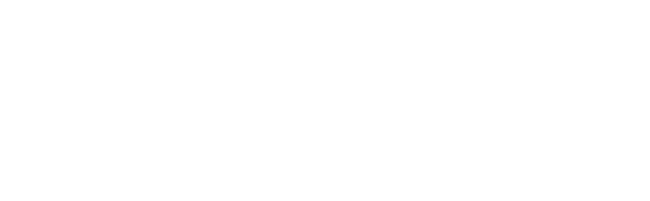現代社会は、見えない壁に囲まれた巨大かつ透明な「無菌室」へと変貌を遂げつつある。我々が呼吸しているこの空間は、あらゆる物理的・心理的摩擦がアルゴリズムという名の空調設備によって事前に検知され、無害化されるよう設計された徹底的な管理空間である。他者との不快な衝突、予期せぬノイズ、心を掻き乱す異物たちは、「ブロック」や「ミュート」、あるいはAIによる高度なレコメンド機能というデジタル上の不可視化・遮断プロセスによって即座に処理され、我々の視界から永遠に放逐される。
教育の現場を見渡せば、「心理的安全性」という本来は組織論における限定的な概念が、いかなる精神的負荷も許容しない絶対的なドグマとして機能し、子どもたちから痛みを伴う試行錯誤の機会を周到に排除している。また、ビジネスの領域においては「無形商材」という実体を持たないクラウド上の空間において、顧客の生々しい悲鳴や肉体的な苦痛が、単なるデータポイントや最適化のための「処理チケット」として、血の通わないダッシュボードの上で消費され続けている。
我々は今、痛みも、重力も、肉体の軋みも存在しない、極度に最適化された「メタバース(仮想的脳内空間)」へと集団的に亡命しようとしている。しかし、この摩擦ゼロの快適さが我々にもたらしたものは、真の解放であっただろうか。否である。ドイツの哲学者マルティン・ハイデガーが、その主著『存在と時間』(1927)においてすでに警告していたように、この快適さの代償は我々の想像を絶するほど大きい。
「人間は日常の安逸な匿名的空間(世人=ダス・マン)へ『頽落(たいらく)』していく存在である。」
——マルティン・ハイデガー
ハイデガーが指摘した「ダス・マン」とは、自らの生を主体的に引き受けることを放棄し、世間の同調圧力や「みんながそうしているから」という平均的な価値観に埋没して安心を得ようとする匿名の存在である。現代のメタバース的な無菌空間は、この「頽落」を極限まで加速させる装置に他ならない。ノイズのない最適化された世界で、我々は自らの輪郭を失い、他者と同じものを消費し、同じように「いいね」を押し合うだけの匿名の記号へと成り下がっている。
この終わりのない頽落の果てに、我々が今まさに手放そうとしているもの。それこそが、泥臭く生々しい「実存の感覚」であり、予測不可能な他者の「命へのアクセス」である。本稿は、現代を分厚く覆うこの狂気じみた「痛覚と身体性の喪失」に対する、思想的・構造的・そして実践的な批判である。哲学、教育学、現象学、社会学の知見を多角的に交差させながら、我々が再び直視すべき「他者という圧倒的な質量」と、我々が帰還すべき重力に満ちた現実空間「ユニバース(現実宇宙)」の復権を論じる。
メタバース的逃避――デカルト的身体の極北と「地位財」の呪縛
本稿において定義する「メタバース」とは、VRゴーグルを被ってアクセスする3DCGの仮想現実空間といった、単なるテクノロジーの用語に留まらない。それは、「実存(生々しい現実の質量と重み)から乖離し、完全に統制可能な脳内(あるいはデジタル)空間の中で自我を構築・完結させようとする、現代的な逃避のパラダイム全体」を指す隠喩である。我々はSNSのタイムラインや、リモートワークの画面越しにも、すでにこのメタバース的空間を生きている。
この逃避のパラダイムの源流は、近代哲学の祖であるルネ・デカルトにまで遡る。デカルトが『方法序説』(1637)において「我思う、ゆえに我あり(Cogito, ergo sum)」を提唱し、精神(思考)と身体(延長)を明確に切り離す「心身二元論」を確立して以来、近代の理性は常に「思い通りにならないノイズとしての肉体」をいかに統御し、あるいは切り離すかを模索し続けてきた。デカルトにとって、確実なのは純粋な思考だけであり、身体は騙されやすく朽ちゆく機械に過ぎなかった。
現代のメタバース至上主義とは、このデカルト的夢想の究極の帰結である。シリコンバレーの技術者たちが夢見る「意識のアップロード(トランスヒューマニズム)」に象徴されるように、メタバース空間では、老い、病、醜さ、排泄、そして何より予測不可能な「他者の身体」という最大のノイズが、アルゴリズムによって排除、あるいは純化される。
しかし、この摩擦も重力もない空間への逃避は、我々に真の幸福(Well-being)をもたらしただろうか?現実の社会を見渡せば、答えが「否」であることは火を見るより明らかである。
身体という「絶対的な固有性」を手放し、純粋な記号・情報となった人間は、メタバース空間において、絶え間ない「他者との比較」という地獄に堕ちる。経済学や心理学の領域、そして月刊ウェルビーなどの現代的論考でも警鐘が鳴らされているように、自らの身体感覚を伴わない精神は、「非地位財(Non-positional Goods:自分自身の固有の価値、健康、没頭、安心感、自由など、他者との比較に依存しない幸福)」を見失う。その結果、富、名声、社会的地位、そしてSNSの「フォロワー数」や「いいね」といった「地位財(Positional Goods:他者との相対的な比較によってのみ価値が定まるもの)」の果てしない追求へと強迫的に駆り立てられる。
地位財の恐ろしい点は、それが本質的に「ゼロサムゲーム」であることだ。誰かが上に立てば、誰かが相対的に下に下がる。そこには永遠の安息はない。
「人間の真の活動は、自分とは異なる予測不可能な他者が存在する空間(=複数性)においてのみ成立する。」
——ハンナ・アーレント『人間の条件』(1958)
アーレントは、人間が人間らしくあるための条件として「複数性(Plurality)」を挙げた。人間は一人ひとり全く異なる存在であり、その異なる者たちが同じ空間に集い、言葉と行為を交わす空間(公的領域)こそが、真の「活動」の場であるとした。しかし、メタバース的な空間では、少しでも不快な他者、自分と異なる意見を持つ者は、アルゴリズムとブロック機能によって容易に排除・透明化できる。そこにあるのはアーレントが重視した「複数性」のダイナミズムではなく、似た者同士が傷を舐め合い、自らの偏見を強化し続ける肥大化したエゴイズムの反響(エコーチェンバー)に過ぎない。
地位財の追求に対するブレーキが壊れたまま、他者という鏡を持たず、実存を伴わない記号的な自己主張だけを永遠に繰り返す現代人は、情報の大海の中で深い虚無と精神的疲弊の淵に沈み込んでいるのである。
「体罰」の現象学――メルロ=ポンティと他者という圧倒的質量
メタバースの無菌的で記号的な空間に対置されるべきは、絶対的な物理法則と、決して逃れられない肉体的制約に支配された現実空間、「ユニバース」である。ここで我々は、現代社会において最大のタブーとされ、一切の議論が封殺されている「体罰」という概念を、あえてモーリス・メルロ=ポンティの「身体の現象学」の視座から再考論してみたい。
当然の前提として明確にしておくべきは、教育現場やスポーツ指導における暴力、あるいは権力的な支配の手段としての「体罰」は、絶対悪として徹底して排除されるべきだということである。フランスの哲学者ミシェル・フーコーが『監獄の誕生』(1975)において克明に描き出したように、権力による身体への介入は、人間を規格化し、権力にとって都合の良い「従順な身体(Corps dociles)」を作り出すための野蛮な規律訓練(パノプティコン的支配)に他ならない。これは現代の人権意識において完全に否定されるべき歴史の遺物である。
しかし、暴力の否定という極めて正しい倫理的進歩の陰で、我々は「哲学的な文脈における『肉体への直接的介入』が持っていた根源的な機能」までをも、無意識のうちに忘却・廃棄してしまったのではないか。
「私の身体は単なる物質ではなく、世界と交差する『肉(chair)』である。」
——モーリス・メルロ=ポンティ『知覚の現象学』(1945)
メルロ=ポンティは、デカルト的な「精神と物質の分離」を乗り越え、我々が世界を認識するのは「身体」を通じてのみであると説いた。彼の言う「肉(chair)」とは、私と世界を隔てる境界線ではなく、私と世界を繋ぎ、交差させる可逆的なメディアである。私が右手で左手を触るとき、私は「触れる主体」であると同時に「触れられる客体」でもある。我々は、世界に触れると同時に、世界から抗いがたい力で触れ返される存在なのだ。
この現象学的な文脈において、広義の「体罰(=外部からの予期せぬ物理的衝撃や痛み)」が示唆していたのは何であったか。それは、「その他者が、自分の脳内の思い通りになるアバターではなく、自分と同じ空間に、コントロール不可能な圧倒的質量(物理的ノイズ)を持って存在している」という残酷かつ真実の事実を、痛覚という生々しい回路を通じて強制的に知覚させる機能であった。
壁を全力で殴れば、拳は砕け散るような痛みを伴う。その痛みは、「壁という物質が、私の意志とは無関係にそこに厳然と存在している」ことの物理的証明である。他者との激しい肉体的接触、あるいは摩擦によって生じる痛みも同様である。痛みとは、私が独我論的な夢の中にいるのではなく、この重力ある世界と確かに接続されていることを証明する、最も根源的で強烈なフィードバックなのだ。
現代人は、権力による暴力を追放するという正しい倫理的進歩を手に入れた。しかしその代償として、世界や他者からの「物理的な摩擦・抵抗(痛み)」そのものまでも過剰に恐れ、遠ざけ、自らの身体をデジタル空間に「透明化」してしまった。
他者との生々しい衝突、摩擦、体温の交換、そしてそれに伴う傷み。そうした「身体性」という絶対的な基盤を通してのみ、我々は自らの輪郭を正確に知り、他者の存在を記号としてではなく「命」として真に引き受けることができるのである。無菌室の住人は、一生涯、自分が何者であるかを知ることはない。
教育の漂白――デューイの「経験」と共成長の喪失
この身体性と痛覚の喪失が、社会の再生産装置として最も深刻かつ不可逆的な形で構造化されているのが、現代の教育システムである。EdTechの躍進、「GIGAスクール構想」に代表される教育のICT化、そしてAIドリルによる「個別最適化された学び」の推進。これらは一見すると教育の進化に見えるが、その実態は、学校という現場からあらゆる非効率、ノイズ、そして物理的・精神的なリスクを徹底的に排除しようとする「教育の漂白」プロセスに他ならない。
現代の認知科学における「身体化された認知(Embodied Cognition)」のパラダイムが実証するように、人間の知性や自我というものは、脳という密室の中だけで情報処理によって形成されるものではない。それは、物理的な身体を通じた環境との絶え間ない摩擦、環境からのアフォーダンス(意味の提供)の知覚、そして運動を通じた世界への働きかけによってのみ形成される。
アメリカの実用主義哲学者ジョン・デューイは、その主著『経験と教育』(1938)において、教育の本質を「経験の絶え間ない再構成」と定義した。デューイにとって学習とは、机に向かって知識を暗記することではなく、自己と環境(他者を含む)とのダイナミックな相互作用(インタラクション)のことであった。そして、真の経験には必然的に未知なるものとの衝突、すなわち「トライアル&エラーという名のリスクと、それに伴う痛覚(失敗の悔しさ、他者との意見の衝突)」が不可避的に伴う。
「真の教育とは『思い通りにならない他者』との遭遇であり、それは一種の暴力的な痛みを伴う『主体の変容』のプロセスである。」
——ガート・ビースタ『教育の美しいリスク』(2013)
現代の教育哲学者ガート・ビースタは、教育を単なる「スキルの獲得(資格化)」や「社会への順応(社会化)」に矮小化する現代の風潮を批判し、教育の核心は、子どもが自分とは異なる異質な世界と出会い、その摩擦の中で自立した主体として立ち上がる「主体化」にあると主張した。ビースタによれば、教育とは事前に計算可能な安全な取引ではなく、何が起こるか分からない、傷つくかもしれない「美しいリスク」を伴うものである。
本来の教育とは、教える側(教師)と教えられる側(生徒)が、生身の人間として互いの実存をぶつけ合い、時に反発し、時に共鳴し合いながら、身体的なフィードバックを交換し合うダイナミックな「共成長」の場であるはずだ。
しかし現代のシステムは、企業のマネジメント用語から拝借した「心理的安全性」という言葉を過大かつ都合よく解釈・担保するあまり(本来の心理的安全性は「意見を言っても罰されない」ことであり「不快な思いをしない」ことではない)、子どもたちから「世界からの痛みを伴う応答」を根こそぎ奪い去ってしまった。
転べば痛いという重力の法則、他者を傷つければ相手が怒り狂うという感情の物理学。現実の泥を被り、他者と真正面から衝突して心臓が早鐘を打つという「身体的フィードバック」の剥奪。これらの過保護な処置は、次世代の精神をメタバース的な無菌室へと幽閉し、結果として彼らから「現実世界(ピッチ)で、自らの思想と肉体を駆使して事象を現象化させる力」を決定的に奪っているのである。傷つくことを知らない子どもたちは、やがて来る過酷な現実の摩擦に耐える免疫を持たないまま、社会へと放り出されることになる。
ビジネスの病理――「無形商材」の虚無とグレーバーのテーゼ
教育現場で進行する実存の漂白と身体性の喪失は、現代資本主義におけるビジネスの構造的病理と完全に軌を一にしている。それが、現代経済の中心を占める「無形商材」の領域にはびこる、決定的な実存の忘却である。
自動車の製造、巨大な建築プロジェクト、医療現場、あるいは日々の食料を生産する農業。こうした「有形商材」を扱う領域には、常にひとつの冷厳な事実が存在する。それは「物理的エラーやわずかな手抜きが、他者の肉体の破壊(死)や生活の崩壊に直結する」という、重力のような逃れられない緊張感である。有形商材を扱う組織や職人は、この「他者の命へのダイレクトなアクセス」を日常的に持っているからこそ、自らが扱う技術や物質に対する本能的な畏怖の念を抱き、倫理的な規律を保ってきた。
対して、現代の経済成長を牽引し、莫大な資本を集めているソフトウェア(SaaS)、ITコンサルティング、金融工学、暗号資産、情報商材といった「無形商材」の領域はどうだろうか。フランスの哲学者ジャン・ボードリヤールが『消費社会の神話と構造』(1970)で看破したように、現代はもはやモノの有用性ではなく、実体を伴わない「記号(シミュラークル)」が自己増殖し、消費される社会である。無形商材は、肉体という重苦しい実存を飛び越え、クラウド上のデータと抽象的な概念の空間だけで完全に自己完結する。がゆえに、これらの産業は「他者の命や生々しい生活へのアクセス権」を構造的に喪失している。
「現代社会に蔓延する『無意味な仕事』は、労働者自身の精神を破壊する暴力性を持っている。」
——デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ——クソどうでもいい仕事の理論』(2018)
人類学者のデヴィッド・グレーバーは、現代資本主義において、誰の役にも立たず、本人ですら無意味だと感じている高給な仕事(ブルシット・ジョブ)が増殖している事実を告発した。コンサルタントが作成する誰も読まない数百ページのパワーポイント、金融マンが構築する実体経済から乖離したデリバティブ商品。無形商材の領域で働く多くの優秀な人々が、なぜ夜更けに深い虚無感と抑うつに襲われるのか。その正体は、「自分の仕事が、生身の他者の命や生活と物理的に何一つ交差していない」という無意識下の絶望である。
さらに恐ろしいのは、命へのアクセスを失った無形商材の組織において、顧客との関係性がいかに変質するかである。身体性を伴うビジネスであれば、顧客の怒りや悲しみは、表情、声の震え、息遣いという「質量を持った物理的現象」として担当者に直接突き刺さる。しかし、無形商材の組織においては、顧客からの「クレーム(怒り・悲鳴)」は、カスタマーサポートの画面上に表示される単なるテキストデータであり、処理すべき「チケット」へと矮小化される。
痛覚を喪失し、合理的なシステムによって「クレーム処理」に慣れきった組織は、社会からの生々しい摩擦をマニュアルとアルゴリズムで弾き返し、自らのKPIの達成と正当性だけを無機質に肥大化させていく。そこには、顧客の痛みを己の痛みとして引き受け、泥臭く「共成長」しようとする熱情など微塵も存在しない。あるのは、最適化されたUI/UXという名の、美しくも冷酷なショーウィンドウだけである。
悪性腫瘍としての企業組織――社会という生命体の破壊
この無形商材企業の暴走を、マクロな生命科学(生物学)の観点からアナロジーとして捉え直してみよう。
人間の身体をはじめとする多細胞生物は、約37兆個の細胞が有機的に連携し、全体としての調和(ホメオスタシス=恒常性)を保ちながら生存している。正常な細胞は、周囲の細胞と情報を交換し、自らの役割を果たし、全体のために必要があれば自死(アポトーシス)を選ぶことすらある。
しかし、この精緻なシステムのなかで、周囲の細胞(社会全体)との有機的な調和を失い、他者への貢献(命へのアクセス)を忘れ、ただ無秩序に自らの増殖のみを目的として暴走を始める細胞組織が存在する。これを医学的に明確に「悪性腫瘍(ガン細胞)」と定義する。
実存の痛みを無視し、顧客の生々しい生活をデータへと変換し続けながら利益を追求する無形商材の企業群は、社会という巨大なマクロ生命体の中において、まさにこの「構造的悪性腫瘍」として機能し始めている。
彼らは、アテンション・エコノミー(関心経済)という名の下に、自らが提供するサービス、アルゴリズム、終わりのないスクロール機能が、画面の向こう側にいる「生身の人間の貴重な可処分時間、睡眠、そして一度きりの人生」を不可逆的に消費させ、精神を蝕んでいるという事実に目を向けることはない。その本能的想像力は、エクセルの数字を追いかける過程で完全に欠落してしまっている。彼らの目的は、ただ次四半期のARR(年間経常収益)を最大化し、時価総額という「記号」を膨張させることだけである。これは宿主の健康を無視して増殖するガン細胞の振る舞いそのものである。
企業が真の意味で破綻(死滅)するのは、貸借対照表の利益がマイナスになった時や、資金繰りがショートした時ではない。
「我々のビジネスは、生々しい人間の命に関与しているのだ」という、重力に満ちたユニバース(現実空間)の感覚が死滅した瞬間、その組織は魂を失い、社会的な存在意義を喪失する。
痛覚を失い、他者からのフィードバックをデータとしてしか受け取れない組織は、やがて社会という宿主を食い破って共に滅びるか、あるいは社会の免疫系(国家による強力な法規制、あるいは消費者の本能的な拒絶)によって物理的に切除される運命にある。
自らのプロダクトやサービスを、メタバースの仮想空間ではなく、現実の社会という血の通ったフィールドに「現象化」させ、その結果生じる摩擦と責任を負う覚悟を持たない組織に、未来の生存権は与えられない。
真のWell-beingへの跳躍――非地位財と身体性の回復
メタバース的思考への極端な逃避、教育システムにおける過剰なリスクと痛覚の漂白、そして無形商材にはびこる実存の忘却と命へのアクセスの喪失。我々を包み込むこの重篤な構造的病理を打ち破り、人間性の回復を図るための具体的な処方箋はどこにあるのか。
それこそが、本稿の序章でも触れ、近年、月刊ウェルビーの論考などでも紹介した「非地位財」の再評価と明確化、そしてそれを見出すための「身体性の回復」である。
「Well-being(ウェルビーイング)」という言葉は、現代ではしばしば健康食品やスパの広告文句のように消費されているが、その語源は古代ギリシャの哲学者アリストテレスが語った「エウダイモニア(Eudaimonia:持てる可能性を最大限に発揮して生きる、究極の卓越性と幸福)」にまで遡る。真のWell-beingとは、単に「不快なことがない(無菌室の状態)」ことではない。
現代人は、メタバース的な情報の濁流の中で、常に他者との比較という「地位財」の競争に晒されている。年収、役職、住んでいる場所、そしてSNSでの影響力。これらの基準はすべて「外部」から与えられたものである。
この無限地獄から抜け出すためには、「自分自身は、一体どのような行動をしている時に時間の感覚を忘れるほど没頭するのか」「誰と、どのような環境で過ごすときに、魂の底からの安心感と充足を感じるのか」という、自身の内面に向けられた圧倒的な解像度が必要となる。これこそが「非地位財」の核心である。確固たる非地位財の軸を持たない限り、地位財の追求という狂った資本主義のブレーキは永遠に掛かることはない。
そして極めて重要なことは、この「自分が何に没頭し、何に安心するか」という実存の感覚は、決して頭の中(メタバース的思考)だけでシミュレーションして導き出せるものではないということだ。自己分析ツールや性格診断テスト(MBTIなど)の質問に答えるだけでは、真の自分など絶対に分からない。
非地位財は、実際に身体を動かし、不格好に汗をかき、思い通りにならない他者と摩擦を起こし、失敗して膝を擦りむき、恐怖や喜びに心臓を高鳴らせるという「身体的実践(ユニバースでの現象化)」を通してのみ、血肉として理解できるものなのだ。スポーツ、芸術、泥まみれの農業、手作りの料理、あるいは他者との激しくも誠実な議論。これらはすべて、身体を通じた世界との対話である。
すべての身体知を統合し、自らの肉体というこの世に一つしかない唯一無二のメディアを通して、世界の抵抗を感じながら接続すること。それこそが、資本主義のダーウィニズム(絶え間ない比較と生存競争)の呪縛から抜け出し、地に足の着いた真の「Well-being」を手にするための、唯一にして絶対の道である。
終章:ユニバースの冒険者たちへ――熱情を注ぐ指揮者と演者であれ
我々が今なすべきことは明確である。周囲を覆う見えない壁、この無菌化され、最適化され、痛みを伴わない快適な境域(コンフォートゾーン)を内側から破壊し、圧倒的な質量と重力に支配された生々しい「ユニバース(現実空間)」へ帰還することだ。
「実存は本質に先立つ。」
—— ジャン=ポール・サルトル『実存主義とは何か』(1946)
第二次世界大戦後の虚無と荒廃の中で、サルトルは力強く宣言した。我々人間の「本質(私が何者であるか、どう生きるべきか)」は、神によってあらかじめ決定されているわけでも、現代のアルゴリズムによって「あなたへのおすすめ」として与えられるものでもない。人間はまずこの世界に投げ出され(実存し)、その後に自らの行動と選択によって、自らの本質を創り上げていく「自由の刑に処せられた」存在なのだ。
我々の本質は、仮想空間のアバターを着せ替えるように簡単に手に入るものではない。それは、重力に逆らって立ち上がり、現実の泥に塗れ、計算不可能な他者の感情と身体ごと激しく衝突し合うという、泥臭く、時に暴力的な実践の連続の中でしか形成されない。その無数の傷跡と、心地よい肉体の疲労という「身体的証明」の蓄積の果てにのみ、確固たる自らの本質は削り出されるのである。
忘れてはならない。痛みのない世界に、真の歓喜は存在しない。摩擦のないツルツルとした世界に、魂の熱狂が宿ることは決してない。
だからこそ、肉体の重さを引き受けよ。他者と衝突すること、拒絶されることの痛みを恐れるな。計算外の失敗、予測不可能なエラーを両手を広げて歓迎し、世界からの容赦のない物理的なフィードバックを全身の感覚器官で感受せよ。
我々の人生は、安全なモニターの向こう側で頭の中の戦術をこねくり回すだけの、リセット可能なシミュレーションゲームではない。我々は自らの内なる思想と哲学を、現実世界という過酷なピッチ上に「現象化(具現化)」させるために、身体のすべてを賭して躍動する「熱情を注ぐ指揮者であり、同時に演者」でなければならないのだ。
ビジネスの最前線、特に無形商材に携わるすべての大人たちに告ぐ。ダッシュボードの数字の向こう側に、自らの労働の果てに「生身の命と生活」があることを強烈に自覚せよ。痛覚を取り戻し、社会のガン細胞となることを拒絶せよ。
そして、これから世界を創り上げる若者たちよ。システムと大人たちが周到に用意した、傷つかない安全な小宇宙(メタバース)に安住してはならない。仮想の麻酔を断固として拒絶し、実存の荒野へ、重力のある大地へと踏み出せ。自らを縛る無菌室の境域を破壊せよ。
我々は皆、他者の命と交差しながら泥臭く生き抜く、ユニバース(実存)の冒険者であるべきだ。
参考資料・引用文献
- マルティン・ハイデガー『存在と時間』(中山元訳、光文社古典新訳文庫、2015年等)
- ルネ・デカルト『方法序説』(谷川多佳子訳、岩波文庫、1997年)
- ハンナ・アーレント『人間の条件』(志水速雄訳、ちくま学芸文庫、1994年)
- モーリス・メルロ=ポンティ『知覚の現象学』(竹内芳郎ほか訳、みすず書房)
- ミシェル・フーコー『監獄の誕生――監視と処罰』(田村俶訳、新潮社、1977年)
- ジョン・デューイ『経験と教育』(講談社学術文庫、2004年)
- ガート・ビースタ『教育の美しい危うさ』(東京大学出版会、2019年)
- ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』(星埜守之訳、ちくま学芸文庫、1995年)
- デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ——クソどうでもいい仕事の理論』(酒井隆史ほか訳、岩波書店、2020年)
- ジャン=ポール・サルトル『実存主義とは何か』(ちくま学芸文庫、1996年)
- ロバート・H・フランク『幸せとお金の経済学』(金森重樹訳、フォレスト出版、2017年)※「地位財」「非地位財」概念の参照として
- 高山裕基 各種論考・身体知に関する哲学(月刊ウェルビー等)