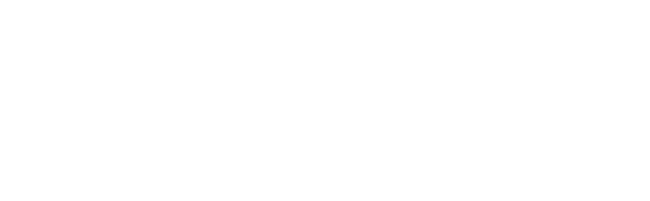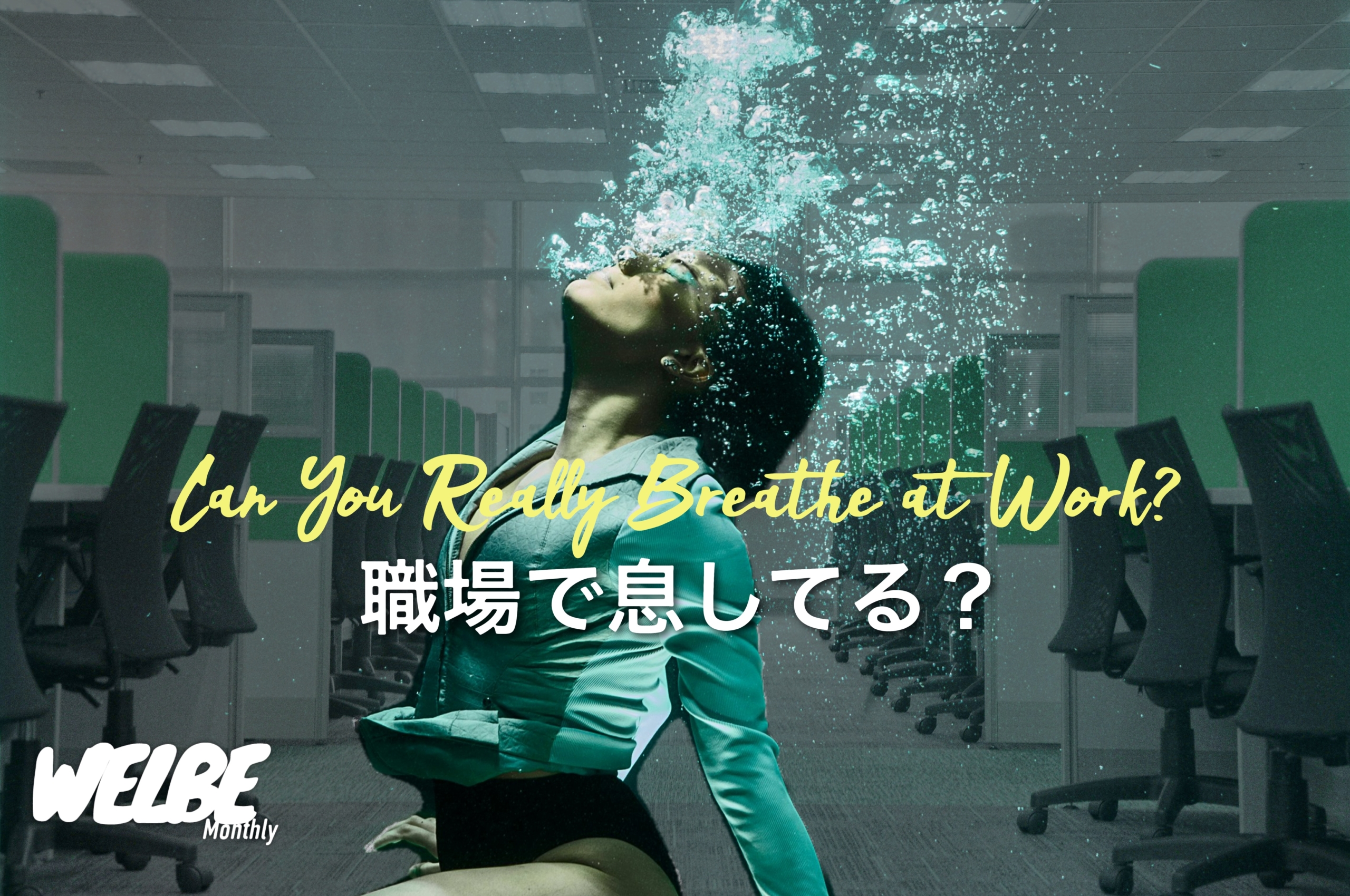元パーソナルトレーナーとして、
いまはDXツールや在宅人材を活用した働き方支援の現場にいる僕は、ずっと「からだの声」と「働き方」のあいだにある違和感を見つめてきた。
生産性は上がっているのに、呼吸は浅くなる。
効率は良くなっているのに、夜は眠れない。
これは、働き方が生き方と“すれ違い”はじめたサインじゃないかと思う。
ウェルビーイングという言葉がある。
でもそれは、癒しや快適さじゃない。
「ほんとうの意味で、生きている」と感じられる仕事を取り戻すこと。
その問いを、からだから始めてみたい。
1|からだが語る「もう無理」は、ウェルビーイングのアラームだ
ウェルビーイングという言葉が流通するようになったが、その語感の軽さに、僕はときおり戸惑う。
それは「整える」とか「癒す」といった語彙とすぐに結びつきやすい。
しかし実際には、ウェルビーイングはもっと根源的な問いだ。生きているとはどういうことか。働くとは何を意味するのか。それを、生活のなかで絶えず引き受ける態度のことだと思う。
その入口として、僕は「からだ」の話をしたい。
パーソナルトレーナーとして、数百人のからだと対話してきた。
触れた筋肉、偏った姿勢、浅い呼吸、沈んだ眼差し。
それらは、単なるフィジカルな情報ではない。
「その人の社会との関係性が、いま、どんな風に歪んでいるか」の記録でもあった。
ある女性の例が印象に残っている。
40代のワーキングマザー。慢性的な肩こりと疲労感を訴えていた。
マッサージでは一時的に緩むけれど、翌週には同じ状態に戻ってしまう。
詳しく話を聞くと、毎日の定例会議に3時間拘束されているという。
内容は抽象的で結論は出ず、出席していることが評価になる場だった。
さらに、保育園の連絡帳は夫ではなく自分が書くのが“なんとなく当然”という空気が家庭内にある。
「書かないと“ちゃんとしてない母親”って思われる気がするんですよね」
彼女は苦笑いしながら、そう漏らした。
「それ、本当に“あなたの仕事”ですか?」と聞くと、
彼女は数秒黙ってから、「わかんないですね……」とつぶやいた。
その瞬間、僕は確信する。
肩こりは、社会的な症状である。
呼吸の浅さは、意味の剥奪によって起こる。
睡眠障害は、自己疎外の物理的な出口である。
つまり、「からだ」は、個人だけのものではない。
それは、その人がどのような文脈に組み込まれ、
どれだけの無意味さに耐えてきたかを雄弁に物語る、社会的な言語なのだ。
ハンナ・アーレントは「労働」と「活動」を分けた。
生きるために繰り返す作業としての“労働”と、
世界に対して何かを始める“活動”。
僕たちが抱える多くの「身体の不調」は、
この“活動”ができていないこと、
つまり、自分の存在が世界に届いていない感覚から来ているのではないか。
ウェルビーイングとは、からだが納得しているかどうか、もっと言えば、「この仕事に自分がいる」と感じられるかどうかにかかっている。
整えることではない。
むしろ、歪みに気づき、痛みに名前を与え、それを引き受け直すこと。
そのプロセスにこそ、「働く」という行為の尊厳が宿る。
2|“生きた仕事”を取り戻す──ブルシットジョブに耐えるな
「この仕事、意味あるのかな?」
そんな問いが、のど元まで出かかって、それでも呑み込んでしまった経験はないだろうか。
たとえば、会議のための会議。“形だけ”の報告書。誰も読まない定例メール。やってもやらなくても誰も困らない──そんな仕事が、今日も僕たちの時間を浸食している。
この感覚に、明確な名前を与えたのが人類学者デヴィッド・グレーバーだった。彼は『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』でこう述べている。
「ブルシット・ジョブとは、それをやっている本人ですら『存在しない方がよい』と密かに信じているような仕事のことだ。しかも、それが社会的・制度的には正当化され、『なくてはならない』とされてしまっている──そこに人間の尊厳を蝕む力がある」
グレーバー(2020, p.27-28)
この「尊厳を蝕む」という語の強さは、僕たちの“からだ”の中で日々起きていることを驚くほど正確に捉えている。
ある企業の中間管理職の男性は、こんなふうに語った。「最近、背中のハリがとれなくて……家庭にも職場にも大きな問題はないんです。でも、毎週つくる定例資料が本当にきつい。誰も読んでないってわかってるのに、“出すことになっているから”という理由だけで、延々と更新を続けているんです」。
それは彼のからだが、「もう意味のない労働に耐えられない」と告げている瞬間だった。
ブルシットジョブの恐ろしさは、単なる無意味さではない。その無意味に、自分の命の時間と意志を明け渡してしまうという構造にある。
誰かのためになっていると感じること。自分の意思から動いていると感じること。その感覚こそが、働くうえでの最小単位のウェルビーイングだ。ブルシットジョブは、その感覚を奪う装置として機能する。
しかも、それらは「形式的な正しさ」に包まれている。期限通りの提出、報告フロー、上司の期待への順応。こうした組織の安定が、個人の“存在の実感”を犠牲に成り立っているとしたら──それは静かな暴力だ。グレーバーはまた、こうも言っている。
「ヨーロッパやアメリカの墓地を訪ねても、“エグゼクティブ・バイス・プレジデント”といった肩書きが刻まれた墓碑はない。それは、人びとが心の底では、自分の仕事を人生の証にしたいとは思っていないことの証左である」
グレーバー(2020, p.311)
それでも僕は信じたい。
少なくとも、“意味のある仕事を生きた”という実感が、その人の姿勢に、声に、顔つきに刻まれていくような働き方があることを。
からだが語る違和感は、単なる不調ではない。
それは構造の裂け目にふれる、確かな知覚だ。
そしてその声に耳を澄ますところから、“生きた仕事”は再び立ち上がる。
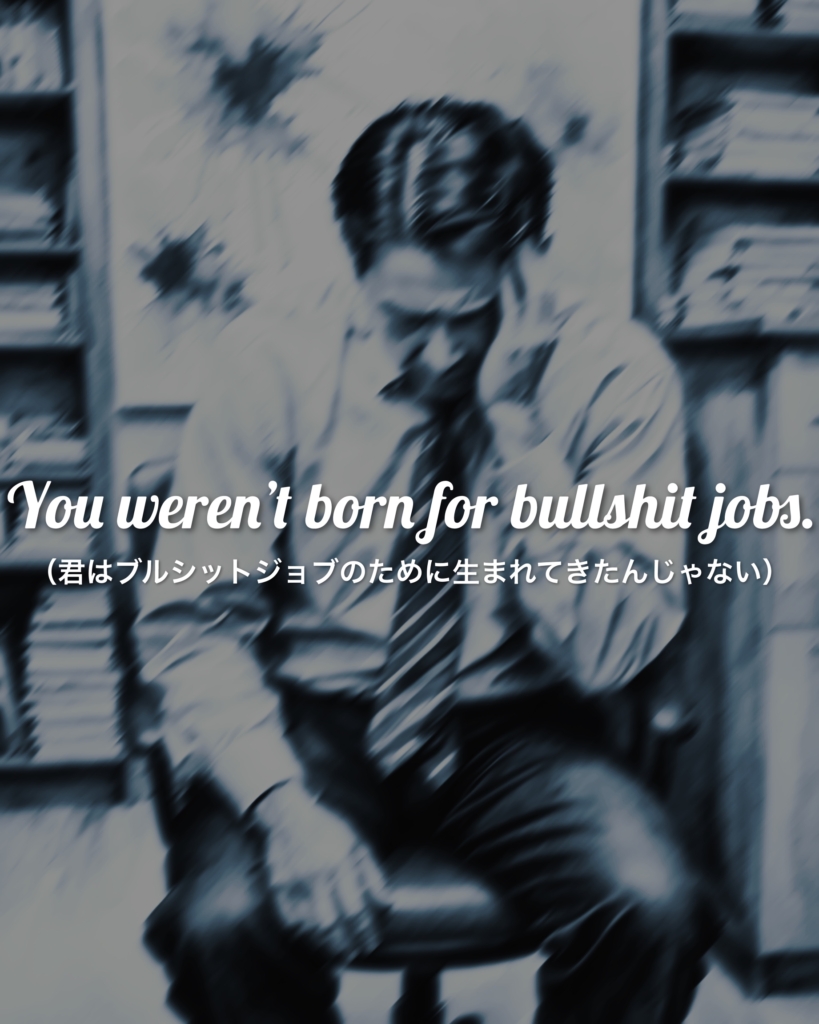
3|ウェルビーイングを支える技術:在宅人材とDXツールの可能性
「働き方改革」とか「DX導入」という言葉が、どこか空々しく響くことがある。
とくに、それが“生産性向上”という単語とセットになったとき。
それは「もっと早く、もっと安く、もっと薄く生きろ」と言われているようにも聞こえるからだ。
だが、本質的な問いは別の場所にある。
この構造は、人が“生きた実感”を得られるようにつくられているか?
僕はいま、企業に対して在宅人材やDXツールを掛け合わせた生産性向上の支援をしている。
たしかに、それはコストの最適化やリソースの柔軟化という面もある。
でも本質は、「意味のある仕事」を社内に再分配し直すことにある。
たとえば、営業部門であれば、属人化していた商談対応をチームベースに移行する。
資料作成やスケジュール管理は在宅ワーカーに任せる。
そのうえで、社員は「顧客の意図を汲み、関係性を築く」ことに集中できるようにする。
バックオフィスも同じだ。
繰り返しの多い業務はツールと在宅人材で仕組み化し、本当に社内に残すべき業務──人の感情が絡み、判断が必要な仕事──だけを手元に残す。
これは効率化ではない。再編成だ。
このとき大事なのは、「在宅人材=外注」ではないということ。
“外にある能力”と“中にある関係性”をどう再接続するか。
それは、単なるリソースの最適化ではなく、組織が自らの意味を再構成する営みでもある。
構造を変えるとは、役割を変えること。
役割が変われば、関係性が変わる。
関係性が変われば、働く人の「存在の実感」も変わっていく。
働きながら呼吸できないのは、単に業務量が多いからじゃない。
自分が「何を担っているのか」が、見えなくなっているからだ。
僕は現場でよくこう尋ねる。
「この仕事、社内で担うべき理由はありますか?」
答えに詰まるとき、そこにはたいてい“誰かの善意で埋められた歪み”がある。
「手が空いてたから」「昔からそうしてたから」「誰も断れなかったから」──
そうした感情的な積み重ねのうえに、名もなきタスクは増殖していく。
だからこそ、技術と人を使って“構造を設計し直す”ことは、ウェルビーイングのための、もっとも根源的な実践になる。
これは「人を楽にする」ためじゃない。
人が“ちゃんと意味を受け取って働ける”ようにするためなのだ。
ウェルビーイングは、内省だけで生まれない。
からだが納得できるような「配置」があり、
関係性が「循環」していて、仕事に「意味の流れ」がある。
その条件を技術によって実現することは、人間中心の組織設計の新しいかたちだと、僕は信じている。
4|違和感を引き受けることが、働くことのはじまり
「なんか、ちがう気がする」。
その“ちいさな違和感”は、しばしば最初にからだに現れる。
呼吸が浅い、肩がこる、食欲が湧かない、夜中に目が覚める。
けれど多くの場合、僕たちはそれを“忙しさ”や“年齢”や“気分の問題”にしてしまう。
違和感は、怠惰のしるしではない。
それは、自分が置かれている場所の“ズレ”に、もっとも早く気づく感覚器官だ。
そして、社会の構造に対してもっとも正直なフィードバックでもある。
たとえば、ある現場で出会った女性。
産休明けで復帰した彼女は、子育てと仕事を両立する「ありがたい制度」の恩恵を受けていた。
時短勤務、リモート対応、配慮されたタスク配分。
でも、彼女はこう言った。
「制度には守られてると思います。でも……なんというか、
ここで働いてる私の“手応え”が、ほとんどないんです」
「楽になった」はずの働き方のなかで、
自分が誰のために、何を担っているのかが見えなくなっていた。
ここに、制度のもろさがある。
制度は「配慮」や「支援」や「公平性」を保証する。
でも、「意味」や「つながり」や「役割の納得感」は、制度の外にしか存在しない。
それを埋めるのが、日々の関係性のなかで醸成される「語られない秩序」だ。
そして、その秩序が不自然になったとき、最初に反応するのが“からだ”なのだ。
違和感とは、世界に対して向ける最小単位の問いかけである。
そこには必ず、「ほんとうはこうじゃない気がする」という個別具体的な実感がある。
そしてそれは、社会を動かす力の最も小さな火種だと僕は思っている。
問題は、その火種を持っている人が「浮く」構造になっていることだ。
違和感を語る人は、しばしば「ネガティブ」「融通がきかない」と扱われる。
でもほんとうは、そういう人こそが構造に“問い”を差し込んでくれる貴重な存在なのだ。
働くということは、まず違和感を見過ごさずに「正気でいること」だ。
からだが感じているズレを放置せず、それを社会の中に持ち込んでいくこと。
そして、それを聞き取れる土壌を、組織のなかに耕しておくこと。
問いがあることは、未完成であるということだ。
でも、未完成であるということは、変わる余地があるということでもある。
そして変化の起点は、いつだって“からだの声”から始まる。
5|生産性とは、呼吸が深くなる設計である
生産性を上げる──。
その言葉が、現場の誰かに「もっと詰めろ」という圧力に聞こえてしまうとき、改善はむしろ人を追い詰めてしまう。
けれど、僕が関わっている生産性向上支援とは、その逆の発想に立っている。
「何を手放せば、人が“本来やるべき仕事”に集中できるか」。
そこから始まるのが、僕の仕事だ。
企業の中には、「コア業務(=収益を生む仕事)」と「ノンコア業務(=管理や周辺業務)」の境界が曖昧になっている現場が多くある。
たとえば営業職なら、本来の価値創出は「顧客との対話」「課題解決」「提案」だ。
でも実際には、「訪問スケジュールの調整」「レポートの体裁直し」「メールの並び替え」といった雑務に多くの時間を取られてしまっている。
つまり、集中すべき収益業務に向かえていない。
そこで、在宅人材やDXツールを使って、業務の再配置を行う。
たとえば、顧客対応に関わる事務作業、日程調整、帳票入力などは、在宅スタッフに委託できるよう整理し、
社員は「感情の機微を読む」「判断し提案する」といった、人間の価値が活きる部分に集中するように設計する。
これが、効率化ではなく「意味の再分配」だと僕は思っている。
ここで、僕が繰り返し使ってきた「呼吸」という言葉について補足しておきたい。
僕にとって「呼吸ができているか?」とは、感覚的な話ではない。
それは、集中と回復のリズムがきちんと設計され、役割と意味の流れが自然に通っている状態を意味している。
働くことが、ただ吐き出すだけでなく、吸って・ためて・また出せるという循環になっているか。
それが“呼吸できる構造”ということだ。
ある現場で、業務の自動化によって社員1人あたり週に2時間の余白が生まれた。
だがその時間はすぐに「より戦略的なタスク」として再配置され、
誰も「呼吸が楽になった」と感じていなかった。
生産性とは、単にタスクの量を減らすことではない。
人が意味ある仕事に集中できるように“構造を整える”ことだ。
だからこそ、僕はこう問い直す。
この人が、本来やるべき仕事は何か?
その集中を妨げているのは何か?
それを誰が担えば、意味がより良く循環するか?
生産性向上の支援とは、そうした問いを組織に挿入し、その答えをチーム全体で形にしていくプロセスだ。
業務の再設計は、「役割の再設計」でもある。
その結果として社員が「自分が担っている意味」を受け取れるようになる。
それが、呼吸の深さを取り戻すということだ。
生産性とは、深く働けるようになること。
そのとき、組織は速くなるだけでなく、しなやかで、持続可能な空気を持ち始める。
そして、ウェルビーイングとは、まさにその空気の中でしか育たなのではないか。
6|労働主体を育てることが、ウェルビーイングの処方箋である
僕たちは、働くことで疲れているのか。
それとも、働いても“手応えがない”ことで疲れているのか。
現場で出会う多くの人が、後者に苦しんでいる。
やるべきことはこなしている。数字も出ている。けれど夜、深く眠れない。
「この仕事に意味があるのか?」という問いが、心のどこかで解かれないまま残っている。
この違和感の背景には、「働く主体」の質の変化がある。
働くという営みを「手段」として捉える人が増えている。
この構図を、内田樹氏は『下流志向』の中でこう語っている。
「いまの若者には、学びや労働が“消費行動の延長”として受け取られている側面がある。
労働とは何かを得るためにするものであって、“損をするならやらない”。
それは、学びや労働における自己変容を拒む姿勢でもある」
― 内田樹『下流志向』(講談社文庫, 2007)
この文脈で、僕が大事だと思うのは、「消費主体」と「労働主体」の違いだ。
- 消費主体とは、働くことを「何かを得るための手段」として捉える。
つまり、評価・報酬・成果といった外的価値の獲得が主目的になる。 - 労働主体は、働く行為そのものに意味を見出す。
そこにあるのは、「自分の関わりが、世界を少しでも変えている」という実感であり、働くこと自体が報酬となる生のあり方だ。
僕が出会ってきたZ世代の若者たちは、実はこの「労働主体」の感性を鋭く持っている。
彼らは口にこそ出さないが、「この仕事が、自分の時間と交換する価値があるか」を本能的に問い続けている。
そして僕は、その問いの感性を信じたい。
企業の中で労働主体を育てるということは、単に制度を整えることではない。
「働くことが自己形成につながる」という回路を、構造的に開くことだ。
そのためには──
- ノンコア業務を再配置し、収益業務に集中できるようにすること
- 仕事のなかに「自分の判断」「関与」が織り込まれるようにすること
- 「誰のためにやっているのか」が見える仕事を意識的に設計すること
こうした仕組みが、労働そのものに内発的な価値を感じられる状態を育む。
問いをもてる人、違和感を語れる人が「浮かない」組織。
それが、労働主体の土壌だ。
そこでは、働くことが「自己変容」であり、
報酬が“後からついてくるもの”として受け取られる。
僕は信じている。
ウェルビーイングは、支援や配慮ではなく、主体性の発火点を守ることから始まる。
労働とは、命の時間を世界に差し出す行為だ。
その時間が「誰かに使われた」のではなく、「自分で差し出した」と感じられるとき──
人は、働きながら生きていける。
おわりに|この働き方、ちゃんと呼吸できているか
僕は、呼吸について語ってきた。
それは、からだのことだけじゃない。
“働くこと”そのものに、呼吸があるかどうか。
吸って、ためて、吐く。そのリズムの中に、自分の意味が宿っているかどうか。
仕事が「こなすもの」ではなく、「応答するもの」になっているか。
問いがあるか、応答があるか。関係があるか。意味が流れているか。
ウェルビーイングとは、特別なことではない。
それは、“あたりまえに生きられる”という感覚の、土台のようなものだ。
その土台が失われると、人は“耐える”ように働くようになる。
本来、労働とは世界との関係を取り戻す行為であり、
生きているという実感を持てるもっとも根源的な営みだったはずなのに。
Z世代の若者たちは、よく「やりがい搾取を避けたい」と言う。
でも、僕は彼らの中に、「ちゃんと働きたい」という切実な願いを見ている。
意味のない業務ではなく、自分の力が誰かの役に立っていると感じられる仕事に関わりたい──
それはつまり、「労働主体として、関われる仕事がしたい」ということだ。
僕のしている支援は、生産性を上げることでも、仕事を効率化することでもない。
本質は、「働くことに“呼吸”が戻る構造をつくること」だ。
在宅人材やツールを使うのは、そのための手段にすぎない。
人がコア業務に集中し、
意味のある時間を使い、
終わったときに「ちゃんとやれた」と思える。
それが、呼吸が整った働き方だと、僕は思う。
働くことでからだが壊れる社会は、どこかが壊れている。
呼吸できない職場では、誰も長く生きられない。
だからこそ、問い直したい。
この働き方、ちゃんと呼吸できてるか?
参考文献一覧
- デヴィッド・グレーバー(2020)
『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』
酒井隆・芳賀達彦・森田和樹訳、岩波書店
(原著:David Graeber, Bullshit Jobs: A Theory, 2018) - ハンナ・アーレント(1994)
『人間の条件』
志水速雄訳、ちくま学芸文庫
(原著:Hannah Arendt, The Human Condition, 1958) - 内田樹(2007)
『下流志向──学ばない子どもたち 働かない若者たち』
講談社文庫 - 磯野真穂(2023)
『他者と生きる──リスク・病い・死をめぐる人類学』
晶文社
※身体性と社会構造の相関に関する背景理解として参照 - 熊谷晋一郎(2018)
『リハビリの夜』
医学書院
※「からだの声」を社会的文脈にひらく視点として言及